話題の本
話題の本一覧
- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。
- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!
- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。
- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!
- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ
- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく
- そのつらさには正当な理由がある。
- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!
- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!
- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察
草思社ブログをご覧ください
1761年創業の古書店でのおかしな体験記
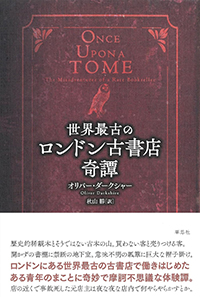
「ここで働くのにまともである必要はないが、酔狂であるのは役に立つ」
1761年創業という由緒ある古書店「サザラン」の店のモットーだそうです。近年、そこで見習いとして勤めはじめた著者の最初の驚きが……
「サザランの品ぞろえのうち、古書以外の骨董品がかなりの割合を占めていたのには驚いた。店の伝統として、文学書は意味もさだかではない〈古物およびその他一般〉という売り場の棚で、多岐にわたる普通の骨董品といっしょに売られている。つまり、この売り場の名称は、ほかにどう扱っていいものやら、実は誰にもよくわかっていないことを丁重に言い換えただけにすぎない。」(第1章「古物およびその他一般」より)
来店する冷やかし客
「ぽつりぽつりではあるがかなりの人が店に入ってきて、何事もなければ、おそるおそる入ってくる人の流れは途切れることがない。…ほとんどの人は呆然とした様子で店内を見てまわり、あるいは質問をしてくるが、実際に本を買ってくれるのはごく少数の人にかぎられる。悲しいことに、一見して買ってくれる客かそうでない客かは見分けられない。」(2 冷やかし客)
古書店を支えるコレクターたち
そんな店の経営を支えてくれるのは「コレクター」という存在。
「『蔵書』という御旗のもと、そこには風変わりですばらしい人たちが集っている。彼らは本という紙の宝物を収集すること、そして、その宝の山に埋もれていたいという執着によって結ばれている。彼らのなかには定期的に来店するのを主義としている者がいれば、やり取りは郵便だけという者もいる。」(2 コレクター)
こうした「コレクター」は、じつは2種類に分かれるという。
ひとつは多岐にわたるジャンルを収集する人たち。
「このタイプに共通するいちばんの性質はその博識だ。五〇の分野に食指が動かせるなら、たったひとつのジャンルだけでは彼らは満足しない。自分のコレクションに何があるのかことごとく知ってはいないかもしれないが、古書店で出物が見つかれば、見逃すリスクを冒すより、むしろ三冊購入したほうがいいと考える。」(同前)
もうひとつは明確に限定されたジャンルのみを収集する人たち。
「彼らの収集は(限定された)対象を中心に繰り広げられる。…その研究分野に連なるものなら、彼らはなんであろうと調達してわがものにする。このタイプに本を売るチャンスは、彼らが関心のある分野にどれだけ精通しているかに比例している。」(同然)
古書店員はこうした手ごわいコレクターに対峙できる知識と根性が要求されるようである。
古書店にかならず出没するせどり屋
本が売れると、ほかの本と在庫を入れ替えなければならないのが古書店の悩ましいところ。
「新刊書店とは違い、希少本を注文して隙間を埋めることなどできない。同業者から本を買って仕入れると、利幅は本当にかぎられてしまう。本当に価値のある本は放し飼いにされており―つまり、正常な取引ルート以外から入ってくる。…そうした本を手に入れるために古書店は、それこそ1001もの方法を駆使している。…おそらく、あらゆる仕入れ先のなかでも古書ならではの存在で、しかも日頃からかかわっているのがブックランナー―つまりせどり屋だ。」(3 せどり)
「せどり業界というものがあるわけではない。彼らに耳打ちしてくれる人や指示してくれる人もいないと思うが、古書店に行くと、どういうわけかなんの断りもなく、かならずと言っていいほど彼らは現れる。自然の摂理のようにも思えてくる。」(同前)
この「せどり屋」、いろんな人がいるが、なかには亭主が遺した膨大な蔵書を売るうちにいつかせどり屋に「進化」した未亡人もいるという。
サザラン接客マニュアル
さて、時間をかけて接客させておきながら「買わない」客も多く、それに対するサザランの「接客マニュアル」があるそうです。(以下抜粋)
「これという本がほかにもたくさんある場合、大半の客は最初に勧められた本を反射的に拒否する。
次に勧められた本については、疑心暗鬼に駆られる場合が多い。
そして、三度目に勧める本はすんなりと受け入れられる(客は自身の選択権を行使しようと決断するのだ)。本当に売りたいと思う本は三度目に勧めるべきである。」(6 接客マニュアル)
たいへん極まりない目録づくり
巨大な迷宮のような店内(上階から地階、地下室まで)を埋め尽くす本の山。その在庫の「目録」づくりというたいへんな仕事がある。
「古書のコレクターほど気難しい人種はいないので、古書店はこの商売ならではの難題に向き合うことになる。つまり、本の状態についてできるだけ正確に説明しなくてはならない。だが、目録の文字数とスペースはかぎられているので、その範囲で本に残る傷と購入するメリットについて説明する必要がある。目録作りの技術とは、業界用語、略語、暗示を総動員して、イメージに偏ることなく本の姿を描き出すことになる。古書店の店員が、くる日もくる日も本の山のなかに頭を隠していたら、目録作りに没頭している可能性が大である。」
貴重な稀覯本と、凡百の古本、本ですらないもの
このあと、本書では崩壊した革装を見事に修復する職人の神がかりの業や、なぜか装幀に毒が練り込まれている本の存在、そもそも由緒ある古書店だから、文学の宝庫であり貴重な稀覯本も多々あるが、そうではない古本の恐るべき山から漂う切ない思いについても描かれていきます。
さらには、何十年も開けられたことのない書棚に、どれに使うかもわからない鍵の束、さらには本ですらないものの存在(ビクトリア女王の顔が彫られたヒョウタン。それを高額で仕入れた先輩。もちろん売れない)。謎の地下倉庫、そこに現われる謎の女性……などの奇妙なエピソードが続きます。
サザランの呪い
そして「それなりの格式がある古書店には謎と呪いがつきもの」とのこと。
「(創業家サザランの姓を)最後に名乗ったヘンリー・サザランは、店を
出た直後、路面電車にひかれて死亡した。当時の新聞に書かれている話は微妙に異なるが、店のすぐ近くで死んだという点では一致している。
いまでもヘンリーの幽霊が店に現れるのはそれで説明がつきそうだ。
幽霊としてのヘンリーは、まがまがしくもなければ、決して理不尽でもない。不意にかんしゃくを爆発させる癖はあったが、彼は礼儀をわきまえた幽霊だ。だから誰もいないのに、棚から本が飛び出すなど、不可解な出来事はどれもヘンリーのしわざだ。
厳密に言うなら、ヘンリーが何に腹を立て、鍵のかかったケースの扉をきしませながら開けたり、あたりに置いてある本のページをはためかせたりするのか、その原因は不明だが、僕たちが何かを決めるたび、そのほとんどを不愉快に考えていることはまざまざと感じられた。」
いかにも由緒ある英国の古書店らしい(英国人好みの)話のようです。
「世界最古の古書店」の世界へようこそ。
こうした奇妙で不思議で、古本好きの向きにとっては魅力あふれるエピソード満載の本書をぜひお楽しみください。
(担当/藤田)
